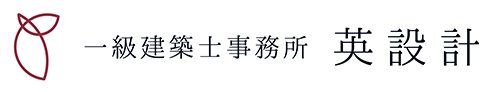暮らしのコラム
「耐震等級3」にすると、広々した間取りが実現できませんよ。という風に聞きました。
という、お話をお客様からご質問いただき、
びっくりしてしまいました。

ご質問いただいたお返事に、お施主様の皆様に同じようにお話をしておりますが、
そんなことはありません。耐震等級3でものびのびした間取りは実現できます。
当社でも、
耐震等級3を実現しながら、
のびのびとした間取りを実現している施工例があります。
あえて、申し上げるならば、
耐震等級3を実現しながら、のびのびとした間取りにするためには、
設計のテクニックが必要。
ということが言えるかもしれません。

8畳間(3,640 x 3,640) を お部屋の大きさの最大値としてとらえて、
6~8畳間を上手に組み合わせて、構造体を接続していく。
ということが、重要になります。
そして、あえて
建物形状を真四角にしないこと。
も重要な要素です。
真四角、正方形層二階 = コストを抑えることが可能。
ということもありますが、
その反面、「のびのびとした間取り」を実現することが難しかったりします。
建築は、必ずバランスが重要です。
何かを際立たせた時には、何かを失うこともあります。
その、
「プラスとマイナスのシーソーゲームのバランスを
お施主様と一緒に、上手に探していくのが設計」 だと思います。
それを実現するために、
耐震等級3を実現するための重要なポイントを
お施主様にも知っておいていただきたく、
以下の3つのポイントをお伝えしたいと思います。
① 自社で耐震設計を行い、耐震等級3の設計のポイントを知っていること
これは、当たり前のことですが、
耐震等級3の設計を「外注」に出している場合があると、
少々、注意が必要です。
なぜか?
自社で設計をしていないものを、現場で施工が問題ないかを確認することができるか?
という点があるからです。
基本的には、自社で耐震等級3を取得できる計算方法を確立して、
判断の基準が明確であることが望ましいですよね。
② 計算書を作らなくても、どの程度耐力壁の数が無いといけないか、ざっくり判断できる。
「えっ?!」 と思われるかもしれないのですが、
「経験」ではなく、
耐震等級3の計算書の計算項目の要点が分かっていると、
簡単な間取り図においても、
ざっくりと必要な耐力壁の数を割り出すことができます。
これができると、設計の幅は制限されてしまいますが、
制限された中で、最大限の提案を模索することができます。
③「柱直下率」、「耐力壁直下率」、「偏心率」の3つを確認している
これは、耐力壁や、骨組みのバランス構成を判断する指針ですが、
ポイントとして、抑えておく基本です。

上記の点を考慮すると、
「耐震等級3にすると、広々とした間取りが実現できない」という方は、
「耐震等級3の設計方法のポイントを知らない。」
ということを、暗に示唆していることにつながりかねません。
「お施主様のご要望が、明らかに広すぎる間取りの要望である」場合を除き、
お施主様のご希望されている間取りを、
可能な限り、のびのびとした間取りで「耐震等級3」を実現するためには、
どうやって考えるべきか。
その視点に立って、設計することが重要になってくると感じています。
併せて、
基礎コンクリートの鉄筋の本数や、コンクリートの背丈や大きさの設計も
非常に重要なポイントになってきます。


「耐震等級3の時の、基礎の設計はどのように行っているのですか?」
というご質問も、これからは、
設計者・建築士を見極めていくための、
重要な質問になっていくかもしれません。
【併せて 読みたい】